今回は例外処理について解説していきます。
例外でのエラーの表現
基本的にエラーは例外で表現します。昔はbool型やint型をメソッドの戻り値にして,エラーの場合はfalseや,マイナス1やマイナス2などのエラーコードを返却するという実装もありましたが,そういった実装は,戻り値のバケツリレーのような感じで,呼び出し先から呼び出し元まで,どんどん戻してこないといけないので,コーディングが大変です。毎回戻り値を見てエラーなら?成功なら?というif文だらけになります。
今回のケース
例えば今回のSearchメソッドを見てみましょう。
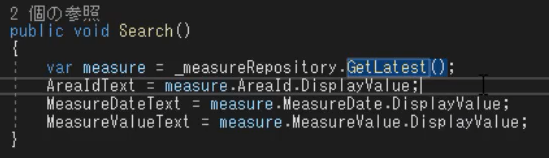
GetLatestが呼び出された後に,戻り値で,正常かエラーかを戻してしまうと,毎回GetLatestを呼び出した次の行でif文が入ります。戻り値をチェックし忘れたら,バグが混入します。
成功した場合だけ次の行に行く
エラー処理の合言葉は,「成功した場合のみ次の行に行く」です。
処理に失敗した場合,何かしらエラーがでた場合は,例外にして,呼び出し元まで落とします。そうすると,メソッドを数珠繋ぎで,ボタンクリックイベントから4つや5つのメソッドを経由した先で,エラーとなっても,そこで例外を発生させれば,一切のエラー処理のコードを書かなくても,ボタンクリックイベントまで落ちてきます。そうすれば,エラーとなった状態で処理をしてしまうことも,戻り値をチェックし忘れることもありません。
今回のGetLatestの例で行くと,SQLServerに接続できなかった場合などは,SQLの例外となります。その場合は,気にせず,呼び出し元まで落とします。
呼び出し元の実装
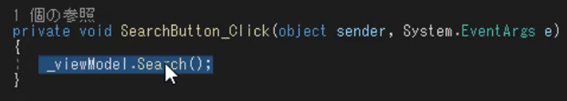
今回の場合,Searchメソッドを呼び出している起点となるSearchButton_Clickまで落とします。ここでキャッチして,エラーメッセージやログの出力を行います。次回はどのようにエラーを表示するかを解説していきます。
#01_プロジェクトの作成
#02_プロジェクトの追加
#03_依存関係
#04_ドメイン駆動開発でApplication層は必要?
#05_Domainのフォルダー構成
#06_Infrastructureのフォルダー構成
#07_WinFormのフォルダー構成
#08_Testsのフォルダー構成
#09_テスト駆動で実装するための事前準備
#10_テストコードとViewModelの追加
#11_テストコードを追加する
#12_ Repositoriesフォルダーの作成
#13_ Entitiesフォルダーの作成
#14_ Mockの作成
#15_フォーム画面の作成
#16_画面のコントロールデータバインドする
#17_Fakeを使ってタミーデータを画面に表示させる
#18_Fakeデータを画面に通知する
#19_PropertyChangedの方法を変更する
#20_Fakeとデータベースの値を切り替える方法
#21_Sharedクラスを作成する
#22_クラスを生成するファクトリークラスを作る
#23_#if DEBUGでFakeデータがリリースされないようにする
#24_DEBUGモードであることをわかりやすくしておく
#25_Factories以外から生成できないようにしておく
#26_Factoriesの呼び出しはViewModelで行う
#27_外部の設定ファイルの値で判断する
#28_Fakeデータを切り替える方法
#29_FakePathを設定ファイルとSharedに移す
#30_Fakeデータのバリエーション
#31_Shareクラスの活用方法
#32_ベースフォームを作る
#33_SharedにログインIDを記憶する
#34_BaseFormでログインユーザーを表示する
#35_ValueObject
#36_ValueObjectを作成する
#37_抽象クラスValueObjectを使用してイコールの問題の解消
#38_AreaIdにビジネスロジックを入れる
#39_AreaIdクラスをEntityに乗せる
#40_MeasureDateの作成
#41_MeasureValueの作成
#42_オブジェクト指向の自動化
#43_Repositoryの具象クラス
#44_例外処理
#45_例外の作成
#46_インナーエクセプション
#47_例外の欠点
#48_メッセージの区分
#49_エラー処理の共通化
#50_ログの出力
#51_タイマー処理はどこに置く?
#52_タイマークラスの作成
#53_StaticValues
#54_Logics
#55_Helpers
#56_Module
#57_トランザクションはどこでかける?
#58_特徴を見極める
#59_さいごに
